目標
MMMと準実験の関係について理解する
MMMと準実験
「マーケティングミックスモデリング(MMM)」と「準実験(quasi-experiment)」は、どちらも マーケティング施策の効果を因果的に推定するための手法 ですが、アプローチが異なります。
マーケティングミックスモデリング(MMM)
アプローチ:主に回帰分析などの統計モデル を用いて、売上などのアウトカムと施策(広告費・価格・販促など)の関係を推定します。具体的には、長期的なデータ(数か月〜数年)を使い、「このチャネルが売上にどの程度寄与しているか」を推定するなどです。
特徴:マクロ視点(売上全体 vs 各施策)からオフライン施策(TV、紙媒体など)も含めて効果を分析できます。データの粒度は「週単位」「月単位」など比較的粗いのが特徴です。
準実験(Quasi-Experiment)
アプローチ:ランダム化比較試験(RCT)が実施できない状況において、統計的な工夫により因果関係を推定する方法です。
代表例: 差分の差分法(DiD)、傾向スコアマッチング、回帰不連続デザイン、合成コントロール法など。
特徴:施策実施群と非実施群を比較して効果を推定します。ミクロ視点(特定キャンペーンや特定地域、特定顧客セグメント)で、データの粒度は「顧客単位」「日次」など細かいことが多いです。
RCTの事例
医療分野(もっとも典型的なRCTの場面)
- 新薬の効果検証
- 被験者をランダムに「薬を投与する群」と「プラセボ(偽薬)群」に分ける。
- 例:高血圧治療薬の臨床試験 → 実薬群の血圧低下効果を検証。
- 新型コロナワクチンの臨床試験
- 数万人の被験者をランダムに「ワクチン接種群」と「プラセボ群」に割り付け。
- 発症率の差からワクチン効果を推定。
👉 医療ではRCTが「ゴールドスタンダード」とされています。
公共政策の事例
- 教育支援プログラム
- 生徒をランダムに「補習授業を受ける群」と「受けない群」に分ける。
- 学力テストの差から補習の効果を検証。
- ベーシックインカム実験
- 一部の地域や住民をランダムに選び、無条件の現金給付を行う。
- 就労意欲や生活の安定度を比較。
マーケティングの事例
- A/Bテスト(広告メール)
- 顧客をランダムに2群に分け、片方には新デザインのメール、もう片方には旧デザインのメールを送信。
- 購入率やクリック率の差を比較。
- Webサイトのデザイン比較
- サイト訪問者をランダムに「新UI群」「旧UI群」に割り付け。
- 滞在時間・購入完了率を比較。
👉 マーケティングでは「A/Bテスト」が、RCTのビジネス応用例そのものです。
RCTの流れ(例:マ―ケーティング)
1. 基本の流れ
- 目的を決める
- 例:広告メールの「購入率を上げたい」
- 施策を2パターン用意
- A: 従来のメール
- B: 新しいデザインのメール(割引クーポン付きなど)
- 顧客をランダムに2群に分ける
- ランダム化により、性別・年齢・購買力などのバイアスを平均化
- メール配信 → 購入率を比較
- 購入したかどうか(0/1データ)を集計し、統計的に差を検証
具体的な例
- テスト設計
- 対象顧客:10,000人
- A群:5,000人に従来メール送付
- B群:5,000人に新メール送付
- 結果データ
| 群 | 配信人数 | 購入人数 | 購入率 |
|---|---|---|---|
| A群 | 5,000 | 250 | 5.0% |
| B群 | 5,000 | 350 | 7.0% |
分析
- 差:7.0% − 5.0% = 2.0%
- カイ二乗検定 / z検定 / ロジスティック回帰 を使って「差が偶然かどうか」を統計的に検証
- p < 0.05 なら「新メールは有意に効果がある」と判断
応用パターン(PDCAサイクルを回しながら改良)
- Webサイト改善
- A: 旧デザイン
- B: 新デザイン(CTAボタンを目立たせる)
- 比較指標:購入完了率、クリック率、滞在時間
- 広告キャンペーン
- A: テキスト広告
- B: 画像つき広告
- 比較指標:クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)
注意点
- サンプル数が小さいと差が偶然に見えることがある(検出力不足)
- ランダム割付が偏ると結果がゆがむ(乱数割付やツール利用で防止)
- 複数回テストを繰り返すと「多重検定」の問題(p値が偶然有意に見える)
MMMと準実験の関係
共通点
どちらも「施策が売上や行動に与えた効果」を推定するための手法で、データドリブンマーケティングのひとつです。
違いとして、MMMはマクロ分析(全体最適)、準実験は ミクロ分析(特定施策の因果効果)のとらえ方があります。双方ともメリットとデメリットがあり、MMMでは、全体のROI把握、予算配分 を強みとしていますが、因果推論の精度が限定的(共変量の制御に依存)という弱点があります。対して、準実験では、全施策を一度に俯瞰するのは難しいという弱点がありますが、特定施策の因果効果を精緻に測定できる強みがあります。
補完的な使い方
実務では、
- MMM → 全体的な予算配分のガイドラインを作る
- 準実験 → 個別キャンペーンや特定チャネルの効果検証
というように 併用されることが多いです。例えば、MMMで「TV広告が売上の20%に貢献」と分かったとしても、「特定地域でのスポットCMは本当に効いたのか?」は準実験で検証する、という使い分けです。
今回は以上となります。
ブックマークのすすめ
「ほわほわぶろぐ」を常に検索するのが面倒だという方はブックマークをお勧めします。ブックマークの設定は別記事にて掲載しています。

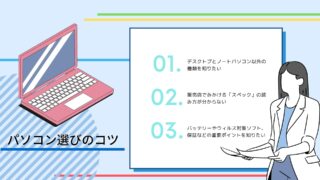
MMMと準実験-1280x720.jpg)

準実験:傾向スコアマッチング(PSM)-640x360.jpg)
クロス集計・カイ二乗検定-640x360.jpg)
準実験:回帰不連続デザイン(RDD)-640x360.jpg)
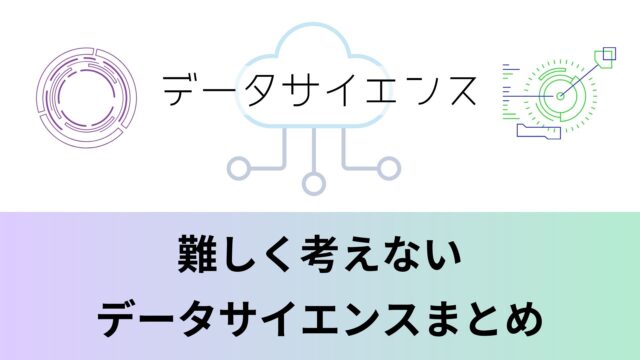
-640x360.jpg)
t検定・ANOVA-640x360.jpg)

カスタム調査とシンジケートデータ-320x180.png)
帰無仮説と対立仮設・有意水準・P値・z検定-320x180.png)
準実験:合成コントロール法-320x180.jpg)
準実験:回帰不連続デザイン(RDD)-320x180.jpg)
準実験:傾向スコアマッチング(PSM)-320x180.jpg)