

このブログを読んでいるあなたが、「Pythonでのシステム開発」を次のステップに進めるための本を探しているのであれば、この記事で紹介する書籍が、あなたの学習に大きな価値をもたらすことは間違いありません。
特に、Pythonを使ったWebシステム開発は、多くの企業や開発者に求められているスキルです。しかし、“Pythonをちょっと触ってみた” だけでは実務に役立つ本格的な開発にはなかなか進めません。ここで紹介する本は、あなたがPythonを 本格的に学んでシステム開発に取り組むために最適な一冊 です。
この記事を参考にしてほしい方
- pythonを基本を学んで、次にシステム開発を行いたい方
python
「python」は言わずもがな「プログラミング言語」のひとつです。プログラムに関わるお仕事をされている方にとっては常に身近な開発言語で、学生にとっても授業に取り入れられるなど、これまた身近なものとなっています。
よく「python」は「汎用的だ。」「適用分野が広い。」と言われますし、実際に多くの開発に利用されています。初心者の方にとっては、そういった良い面をみることは、とても大切ですが、先々、お仕事で利用することを考えるのであれば、感覚第一で触り続ける、学習し続けることは、とても危険と言えます。
「python」に限ったことではないですが、せっかく学ぶのであれば、体系的にしっかりと学ぶのがいいのは想像がつきます。この記事では、このような考えから曖昧さをできる限り取り除ける書籍を紹介したいと思います。
「python」は幅広い分野で使われるので基本文法よりも、結果を優先した学習や利用方法に重みを置いた学習に囚われがちです。分野ごとに必要な学習も確かに大切ですが、基本を押さえることによってこそ幅が広がります。
pythonを利用したWebシステム開発
Pythonを使ったWebシステム開発は、近年とても人気が高く、多くの企業や開発者に利用されています。その理由は、開発のしやすさ、豊富なライブラリ・フレームワーク、読みやすいコード構造などが挙げられます。
PythonでWebシステムを開発する主な方法
PythonでWebシステムを開発する主な方法は、Webフレームワークを利用する方法です。
Pythonでは主に以下のようなフレームワークが使われます。
✅ Flask
- 軽量でシンプル。
- 学習コストが低く、小規模〜中規模のプロジェクトに向いている。
- 必要な機能を自分で組み合わせて構築する「マイクロフレームワーク」。
✅ Django
- フルスタックのフレームワーク(管理画面、ORM、認証などが標準装備)。
- セキュリティや認証などが初めから用意されていて、堅牢なシステムを構築しやすい。
- 中規模〜大規模なシステムに向いている。
✅ FastAPI
- 最近人気急上昇中。
- Pythonの型ヒントを活用し、API自動生成やバリデーションがしやすい。
- 高速でモダンなAPI開発に向いている。
おすすめ図書
(Flask)【初心者から中級者用】
翔泳社:佐藤 昌基 (著), 平田 哲也 (著), 寺田 学 (監修)で「Python FlaskによるWebアプリ開発入門 物体検知アプリ&機械学習APIの作り方」です。こちらは入門書としても、中級書としても利用できる書籍です。
この書籍で学習する大きなメリットは、実践的なWebアプリケーションとAPIの開発方法を学べる点にあります。特に、物体検知や機械学習APIの組み込みに焦点を当て、エンジニアやデータサイエンティストのスキルアップに役立つ内容となっています。
📘の主な内容
- Flaskの基本:最小限のアプリ作成から始め、問い合わせフォーム、データベース連携、認証機能など、FlaskによるWebアプリ開発の基礎を習得します。
- 物体検知アプリの開発:画像データから物体を判別するアプリを作成し、実践的なWebアプリの構築方法を学びます。
- API化とデプロイメント:物体検知機能をWeb APIとして公開し、外部から利用できるようにする方法を解説します。
- 機械学習APIの開発:手書き文字認識などの分析コードを基に、機械学習APIを開発する工程と方法を詳述します。
対象読者
- Pythonで簡単にWebアプリ開発を始めたいエンジニア
- 機械学習に興味のあるWebエンジニア
- Pythonを分析用途でしか使ったことがない人
- 自分でもアプリやWeb APIを作りたいデータサイエンティスト
(Flask)【初心者用】
技術評論社:樹下 雅章 (著)で「Flask本格入門 ~やさしくわかるWebアプリ開発~」です。
📘の主な特徴
- マイクロフレームワークFlaskの基本から応用まで:Flaskの特徴や基本的な使い方から始まり、実際のアプリケーション開発に必要な技術を段階的に学べます。
- 実践的なアプリケーション開発:メモアプリを例に、バリデーション、認証、Blueprintによるファイル分割、外部API連携など、実務で役立つ機能を実装します。
- 最新のFlaskバージョンに対応:Flask 2.3.2に対応し、最新の機能やベストプラクティスを学べます。
対象読者
- Flaskを使ってWebアプリケーションを開発したい初心者
- PythonでのWeb開発に興味がある方
- 実践的なアプリケーション開発を学びたい方
(Flask API)【中級者】
技術評論社:樹下 雅章 (著)で「Python FastAPI本格入門」です。
📘 書籍の特徴
- スキーマ駆動開発の実践:FastAPIの特徴であるスキーマ駆動開発を通じて、APIの設計から実装、運用までの一連の流れを学べます。
- 最新技術への対応:FastAPIの最新バージョンに対応し、非同期処理や型安全な開発手法など、現代的な開発スタイルを取り入れています。
- 実務に即した内容:ソーシャルログインや外部サービスとの連携など、実際の開発現場で役立つ技術やノウハウが盛り込まれています。
対象読者
- FastAPIを用いてAPI開発を行いたい方
- PythonによるWeb API開発に興味がある方
- スキーマ駆動開発や非同期処理を学びたい方
(Django)【初心者から中級者用】
エムディエヌコーポレーション:田中 潤 (著), 伊藤陽平 (著)で「プロフェッショナルWebプログラミング Django」です。
📘 書籍の特徴
- 実践的なDjango開発:Djangoの基本から応用までを網羅し、実際の開発現場で役立つ技術やノウハウを提供しています。
- MTVアーキテクチャの理解:Djangoが採用するMTV(Model-Template-View)アーキテクチャを中心に、各コンポーネントの役割と連携を詳しく解説しています。
- セキュリティとスケーラビリティ:Djangoのセキュリティ機能やスケーラビリティに関するベストプラクティスを紹介し、安全で拡張性のあるアプリケーションの構築方法を学べます。
- 実務に即した内容:ユーザー認証、データベース設計、管理画面のカスタマイズ、APIの構築など、実際のプロジェクトで必要となる機能の実装方法を具体的に示しています。
(Django)【中級者用】
翔泳社:大高 隆 (著)で「動かして学ぶ!Python Django開発入門 第3版」です。
📘 書籍の特徴
- Django 4.2(LTS)対応:最新のLong Term Supportバージョンに対応し、長期的な運用を見据えた開発が学べます。
- Python 3.11対応:最新のPythonバージョンに対応し、新機能や改善点を活用した開発手法を学べます。
- 初心者向けの丁寧な解説:コード1行1行に注釈を入れ、なぜそのようにコーディングするのかを明確に解説しています。
- 体系的な学習構成:Djangoの基礎から応用までを体系的に学べ、実際に動くWebアプリケーションを作成しながら学習できます。
(Django)【中級者用】
翔泳社:芝田 将 (著)で「実践Django Pythonによる本格Webアプリケーション開発」です。
📘 書籍の特徴
- 実務に即した内容:モデル、ビュー、テンプレートといった基本コンポーネントの解説に加え、実践的なテストテクニックやユーザーモデルのカスタマイズ方法、認証処理のベストプラクティスなど、Web開発において必ず知っておくべき内容を幅広く取り上げています。
- 高度なトピックの解説:N+1問題の理解や対策方法、RDBのインデックスチューニングによるSQLの最適化、Web APIの実践的なページネーションの実装方法、CSRFやSQLインジェクションのような攻撃を防ぐためのセキュリティに関する知識など、高度かつ重要なトピックをわかりやすく解説しています。
- 実践的なノウハウの提供:Djangoのコントリビュート経験もある筆者が、現場で役立つ実践的なノウハウを徹底解説しています。
【お知らせ】
本サイト「howahowablog」の「Git&GitHub編」の記事が電子書籍となりました。
バージョン管理(Part1~Part.11)【Git編】の記事はAmazon kindle Unlimited(電子書籍)での販売となります。howahowablog.comではPart.5/10/11のみ試し読み可能となります。
バージョン管理(Part12~Part.21)【GitHub編(前編)】の記事はAmazon kindle Unlimited(電子書籍)での販売となります。howahowablog.comではPart.15/19のみ試し読み可能となります。
バージョン管理(Part21~Part.30)【GitHub編(後編)】の記事はAmazon kindle Unlimited(電子書籍)での販売となります。howahowablog.comではPart.24/30のみ試し読み可能となります。
「Kindle Unlimited」にご登録の方はキャンペーン価格で電子書籍の購入が可能です。
本サイト「howahowablog」の「難しく考えない Excel VBA システム制作編」の記事が電子書籍となりました。
ブックマークのすすめ
「ほわほわぶろぐ」を常に検索するのが面倒だという方はブックマークをお勧めします。ブックマークの設定は別記事にて掲載しています。

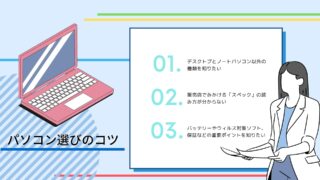


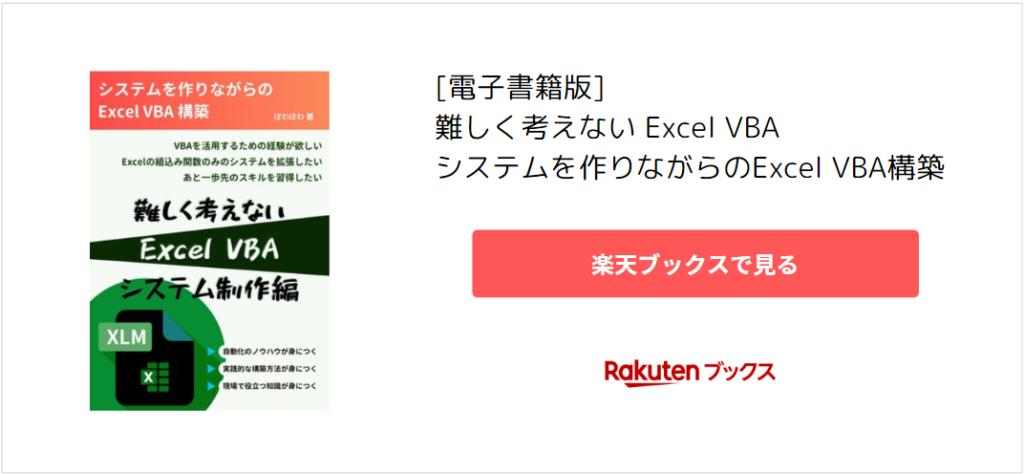
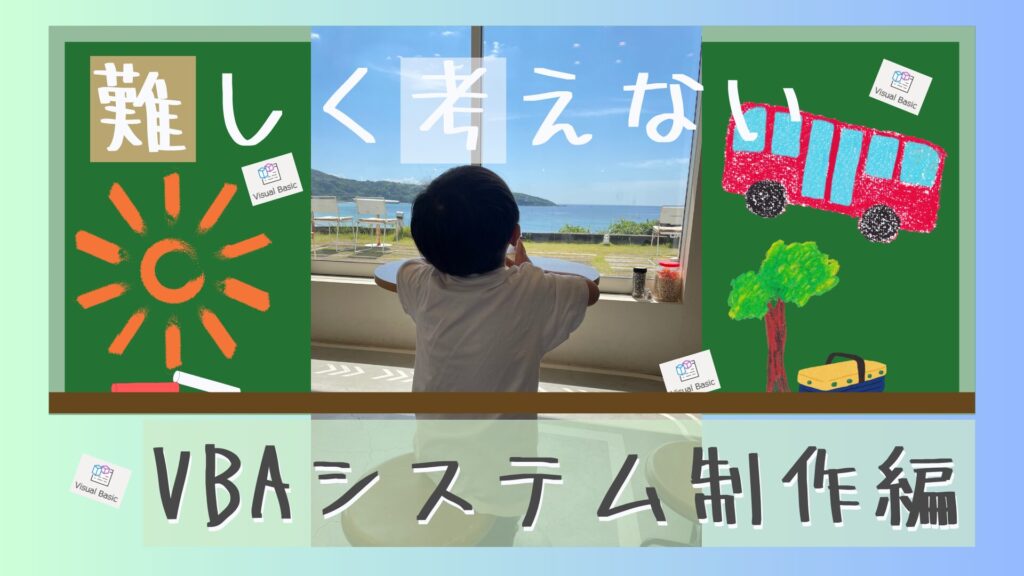


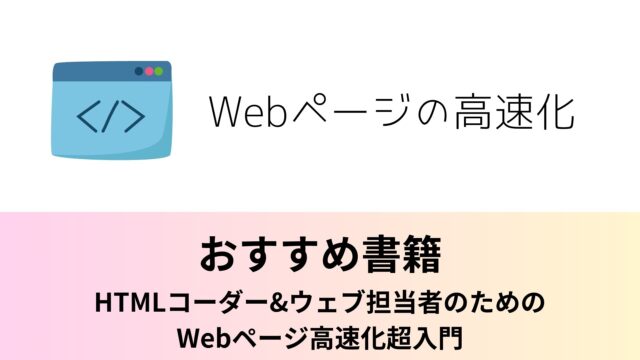
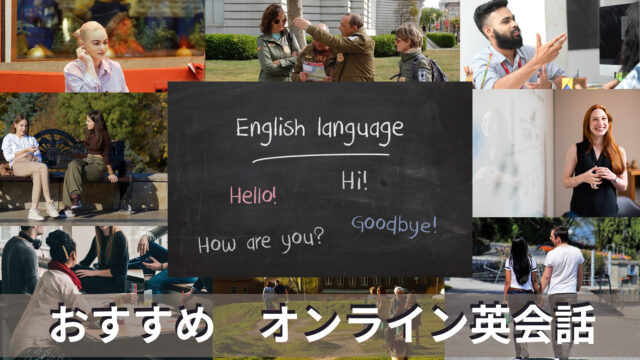
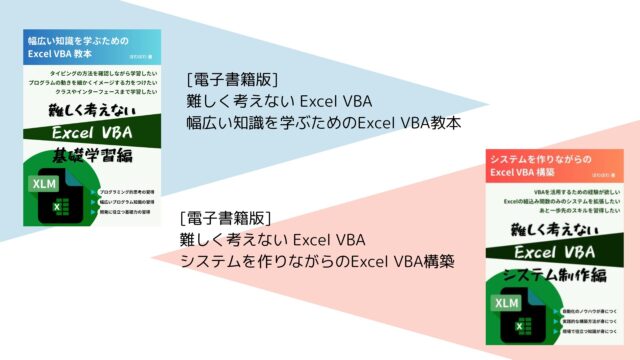
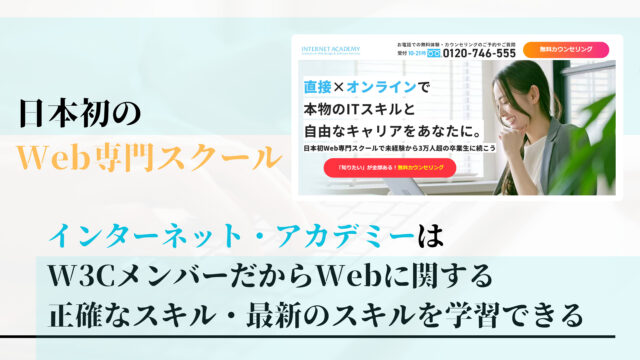
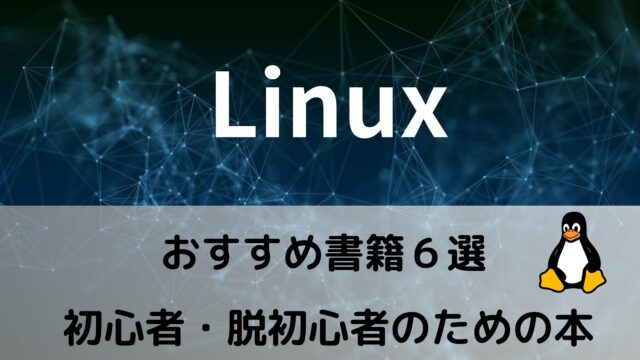

カスタム調査とシンジケートデータ-320x180.png)
帰無仮説と対立仮設・有意水準・P値・z検定-320x180.png)
準実験:合成コントロール法-320x180.jpg)
準実験:回帰不連続デザイン(RDD)-320x180.jpg)
準実験:傾向スコアマッチング(PSM)-320x180.jpg)